
先輩!蠱毒ってなんですか?

蠱毒は、呪術のひとつだよ。もう少し詳しくどんな呪術なのか見ていこう。
蠱毒とは?

蠱毒って、虫がたくさん漢字に含まれてますが、虫を使うんですか?

確かに虫を使うんだけど、この虫の範囲というのがかなり広いんだ。
蠱毒は、多数の虫を使用した呪術の一種です。
中国で古来から使われており、平安時代にはすでに日本に伝わっていた記録が残っています。
中国の法令では、蠱毒を作って人を殺した/殺そうとした場合、または教唆した場合、死刑になると定められています。それほど、中国ではメジャーな呪術です。
呪いのかけ方にはいくつかパターンがあり、その効果も蠱毒の種類によって非常にさまざま。しかし、いずれも呪われた者はろくな死に方をしません。
呪術の中でも材料を集めやすいため、子供が興味本位で蠱毒を実行してしまうこともあります。また、呪詛返しや事故によって、本人が蠱毒の呪いを受けることもあります。
本来は個人に対してかける呪いですが、国家に対して呪いをかけた例もあり、非常に適応範囲が広いことが知られています。
蠱毒の製法
『隋書』によれば、「5月5日に百の虫を容器に閉じ込め、最後の一匹になるまで放置する」と、蠱毒ができるらしいです。
虫とありますが、現代でいう虫とはカテゴリーが異なります。
アリやハチなどの昆虫、蜘蛛やムカデなど昆虫以外の節足動物、蛇などの爬虫類も、ここでいう虫にあたります。
なるべく強い毒を持つ生き物を使用した方が、強力な蠱毒になるとされていますが、使用する生物はなんでもOKのようです。
植物や石などを使用しても蠱毒を作ることができるそうなのですが、そちらのやり方については分かりませんでした……。
作成した蠱毒の使い方

蠱毒の使い方には色々なパターンがあるって言ってましたが、どういうことですか?

それじゃあ、蠱毒の使い方としてよく知られる2つを紹介しよう。
蠱毒の使い方1「呪いたい相手に飲ませる」
1つ目の使い方は、とってもシンプル。それは、「蠱毒となった虫をすりつぶすなどして、呪いたい相手の食事に混ぜて食わせる」というもの。
蠱毒の製法的に、とても衛生的とは言えないのは間違いないのですが、蠱毒を食べさせることによる効果は、単純な食中毒とは一線を画します。
もちろん、呪いが実在しなかったとしても、元々材料に使用した虫が持っている毒や、衛生的でない環境で放置されたことによって真菌を含む微生物の活動で生じた毒素、繁殖した寄生虫などの影響で、健康被害が出るのは、ほぼ間違いないと思います。
蠱毒を使用した場合には、その種類にもよりますが次のような症状が出るとされています。
私の勉強不足かもしれませんが、このような症状を示す毒物を知りません。
ただ、「毛穴から小さな蛇が体に入り込み噛み付く」や「皮膚の下を虫が這いずり回るような感覚に襲われる」というのは、それぞれ寄生虫の経皮感染や、幼虫移行症っぽくも見えます。
寄生虫の幼虫が体内を移動することによって臓器や組織がダメージを負い、症状を呈する。
目に移行すれば失明の危険があったり、皮膚の下を這えば跡が赤く隆起したり、水疱ができることもある。
内臓を通過すれば、臓器の機能不全を引き起こすこともある。
また、幻覚と思わしき症状を呈することもあるようで、それももしかしたら寄生虫が神経に何かしらの作用をして幻覚を見せているのかもしれません。
蠱毒の使い方2「呪いの偶像」
2つ目の使い方は、「蠱毒に恨みの念を送り、呪いの方向を対象に向ける」というもの。
1つ目の方法と違って、対象に食べさせる必要がないのでお手軽ですね(?)
この場合、呪われた人は災いに襲われるとされます。なぜか交通事故によく遭うようになったり、なぜか怪我が増えたり、なぜか病気になったりなどなど……。
強力な蠱毒を使用した場合より大きな災害が起こるとされ、力が控えめな蠱毒を使用した場合でも、災害の規模が小さいだけで対象はほとんどの場合死んでしまうらしいです。

国家を対象に呪いをかけたというのも、こちらの方法ですか?

そう、ある邪教が人間を材料に蠱毒をして、その呪いを日本にかけたんだ。
ある邪教が人間を材料に生み出した蠱毒には、シャム双生児のように頭部が2つあった。
リョウメンスクナが移動した場所では、このような災害が起きたとされています。
| 西暦 | 災害 |
|---|---|
| 大正3年 | 桜島大噴火 |
| 大正6年 | 東日本大水害 |
| 大正12年 | 関東大震災 |
これらは、リョウメンスクナと関連があると考えられている災害のうち、死傷者数が1000人を超えるものを抜粋したものです。
特に、関東大震災のスケールが桁違いで大きく、リョウメンスクナの呪いの大きさが伺えます。
リョウメンスクナについて詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてチェック!
蠱毒の考察「なぜ5月5日?」
5月5日と言われて思いつくのは、端午の節句でしょうか。
端午の節句も蠱毒も、どちらも中国が発祥とされているので、あえて5月5日と明記されているのであれば何かしらの関連がありそうな予感がしていました……。

していました……?

中国における端午の節句の意味と関連付けて、何か考察できないかと思ったけど、なにも関係なさそうだった……。
中国では、端午節は紀元前4世紀、政治家であり詩人であった屈原という人物の供養祭という意味があるらしいです。
陰謀により失脚し、最後は入水自殺をしてしまったのだそうです。その入水自殺をした日が、旧暦の5月5日。
彼の死後も人望は厚く、5月5日を彼の命日として供養祭を行う日として広まったといいます。

それじゃあ、5月5日にはどんな意味があるんですか?

正直、妄想の部分が大きいから、この考察はあまり真に受けないで聞いてほしい……
蠱毒の使い方1で、このように書きました。
蠱毒の製法的に、とても衛生的とは言えないのは間違いないのですが、蠱毒を食べさせることによる効果は、単純な食中毒とは一線を画します。
しかし、やはり食中毒も蠱毒の効果に一役買っているんじゃないか、と思ったわけです。こんなにも、いかにも体に悪いです!と主張しているような製法なのですから。
食中毒が増えてくるのは、細菌が育ちやすい6月から9月にかけてです。このデータは日本のものですが、中国も同じ緯度に存在するので、おおよそ同じと考えてよいのではないでしょうか。
さらに、旧暦の5月というのは、現在の5月下旬から7月上旬にあたります。

食中毒が増える時期と、蠱毒を作る時期が一致してます……!
つまり、5月5日に作ると記述されていたのは、より効果の強い蠱毒を作るために、細菌の力も借りようとしたためと考えることができるのではないでしょうか。
1000年以上の歴史をもつ呪術「蠱毒」まとめ
- 蠱毒は、多量の虫を容器の中に詰め、最後の一匹になるまで放置すると出来上がる
- 出来た蠱毒は、対象に食べさせたり、呪いの儀式の偶像に使用する

途中で表示したリョウメンスクナのリンクを最後にもまた貼っておきます!

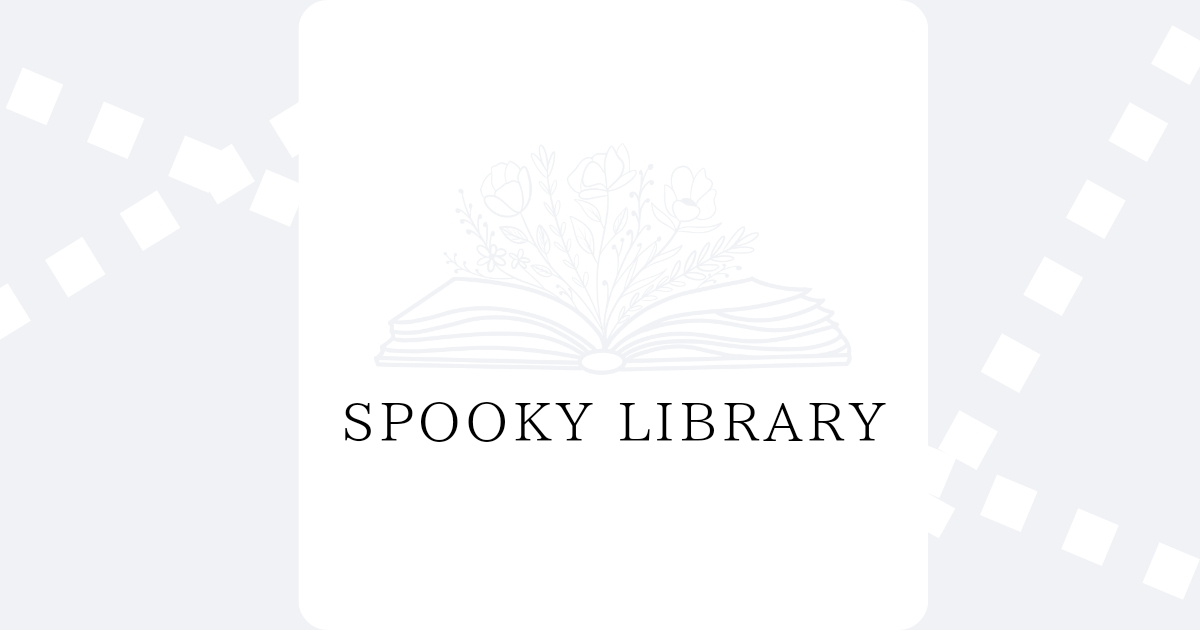

コメント